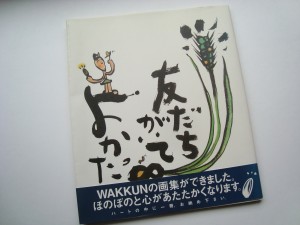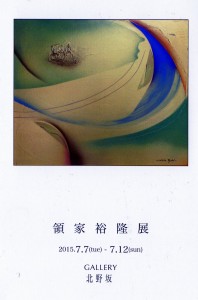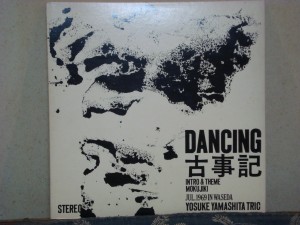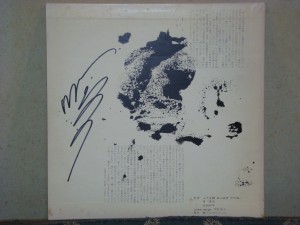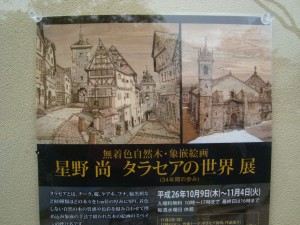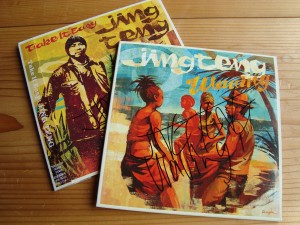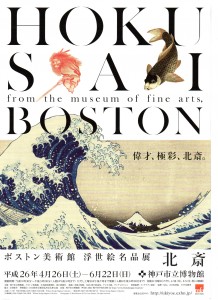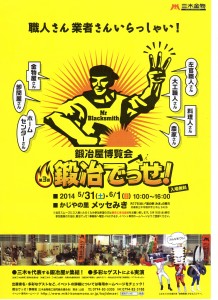昔からある生活道具が好きで、いろいろ集めだしたことが高じて、古物商の許可を取って、工房ギャラリーの片隅で販売を始めてしまいました。
そんな中でもなんとなく竹籠が好きで、いろいろ集めましたが、ここに来られるお客様も購入される方が多く、意外と竹籠が好きな方が多いと感じました。
私が扱っている竹籠は、農作業などの生活用具として作られたものが多いのですが、実用性や堅牢であることを意識して作られたもので、特別に装飾性を意識して作られたものではありません。しかしごく普通の日用品としての機能性の中から自然に生み出された姿が、とても美しく感じます。
そして使い込まれた竹の渋い色合いも魅力的です。
私たちが日ごろ製作している作品も、竹籠のように、実用性の中から生み出されたものが、自然に美しいと感じられるようになればと思いますが、まだまだ遠く及ばない世界のように感じます。