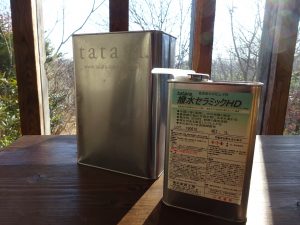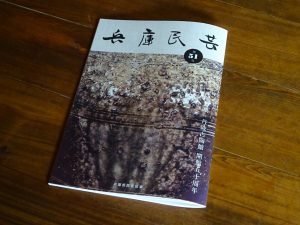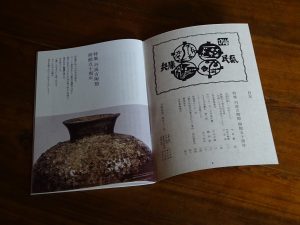最近、漆塗り以外の木の器の塗装でよく使うようになったのが、撥水セラミックによる塗装。
撥水セラミックは、セラミック成分をアルコールで溶解しているもので、木に深く浸透し、固まることで、木の対候性、腐食を防ぎ、水や熱に強く、匂い移りや染み、カビなどに強い塗料です。
食品衛生上の問題もなく、食器に使え、実際に有名うどんチェーン店の釜揚げうどん用の桶などの塗装にも使われています。
飲食店などの業務用の食器の制作を依頼されて、木の素材そのままの透明の塗装での仕上げを希望されて、何にするか悩んでいた時に、たまたま、ミシュランの3星レストラン用の木の食器を納品している知り合いに、これがいいと教えてもらった塗料が撥水セラミックでした。
親切にも、撥水セラミックを小分けして試させてもらい、また塗料の開発者の徳永家具工房の徳永さんも紹介していただき、直接塗料についてのアドバイスもいただきました。
実際に使用してみて、塗膜を作らないため、木の自然な風合いを保っていながら丈夫に木を保護してくれること。食器として匂い移りや、色の移りがほとんどないことがなんと言っても安心感があります。アルコールベースの塗料であるためシンナー臭が無いため、塗装が苦にならず、だれでも簡単に塗れることも嬉しいことです。
撥水セラミックの強度が強いと言っても、木の器を長期に渡って使い続けると、やはり表面が磨滅してきますが、再塗装することで強度が増していくようになります。ただ器のユーザーの方にもメンテナンス用の撥水セラミックを常備していただくことが、ベストと言えるようです。
これからの次世代の塗料としてお勧めしたいと思います。